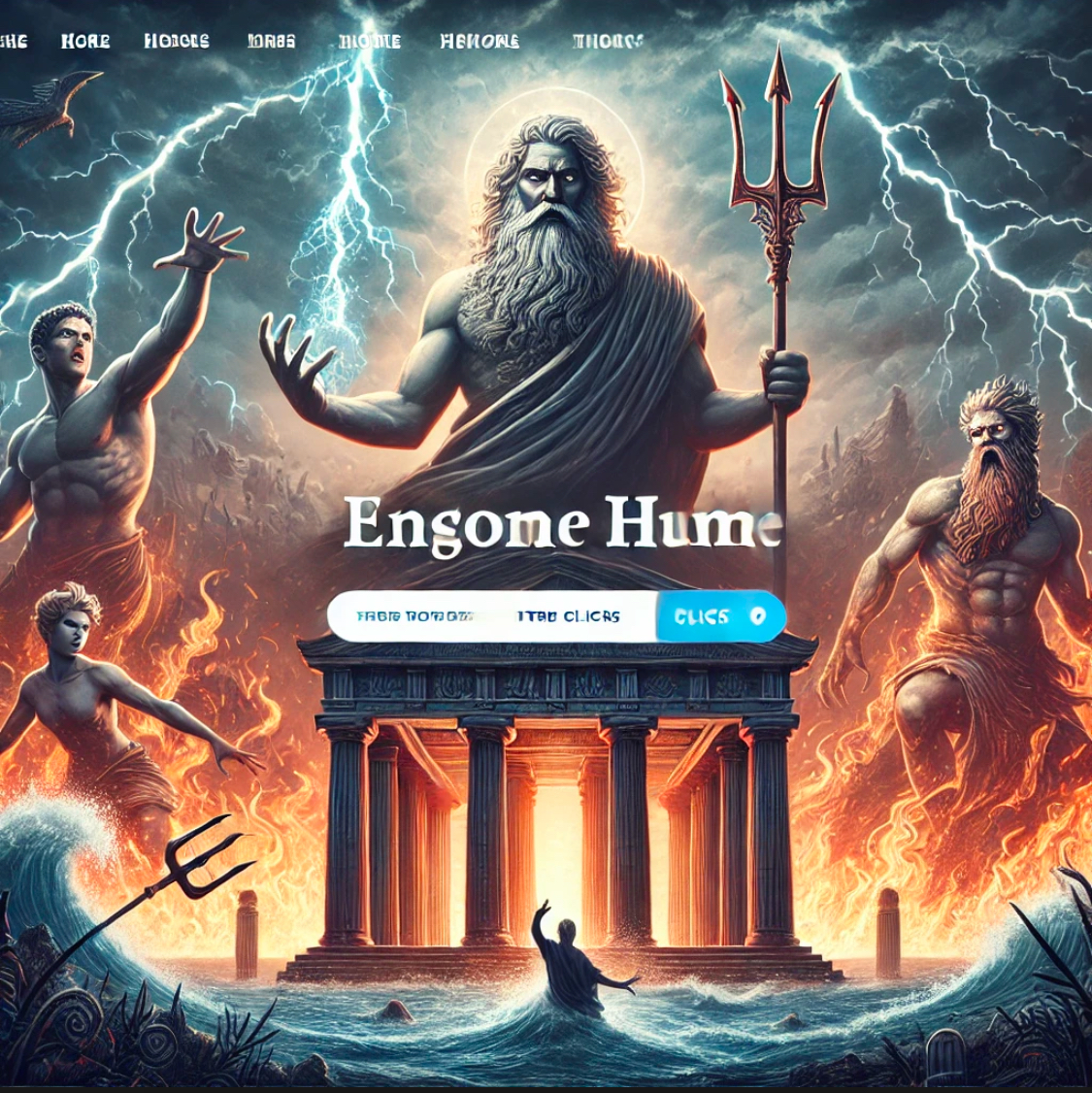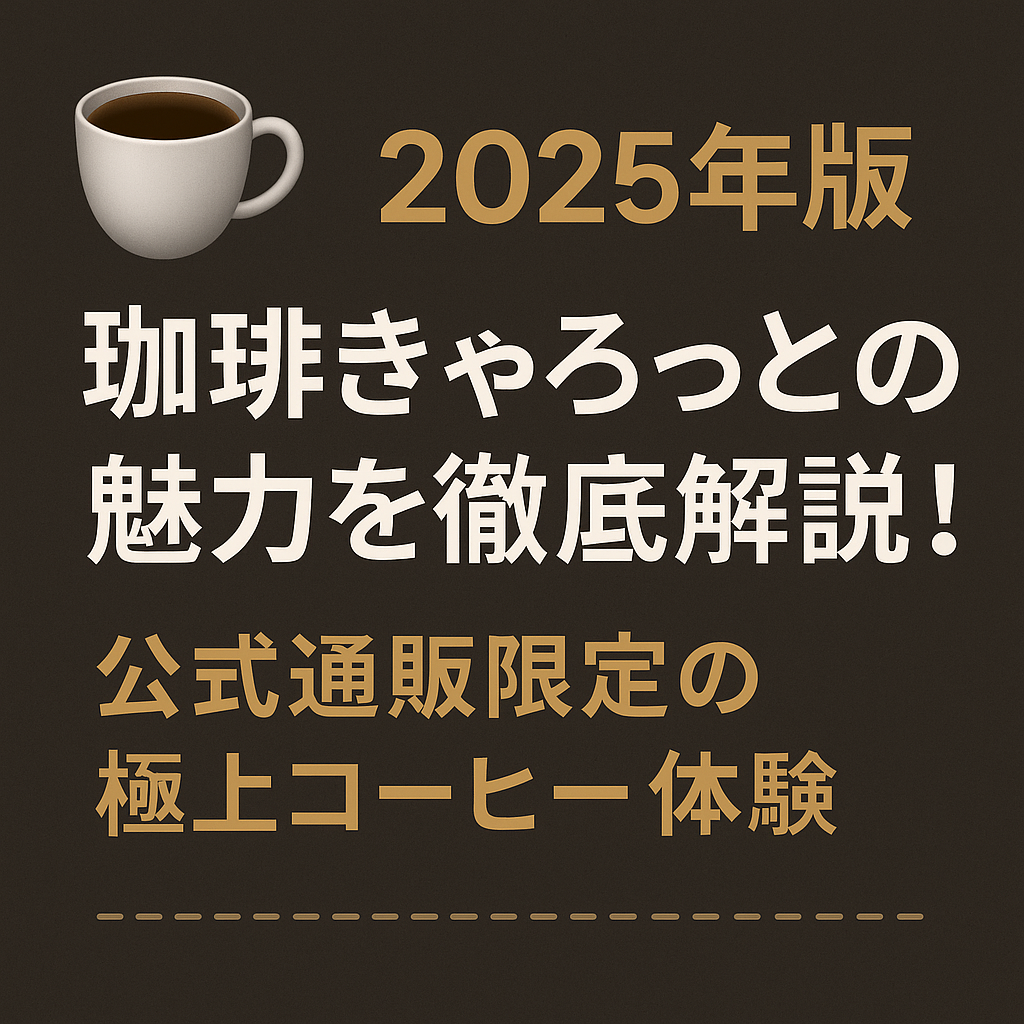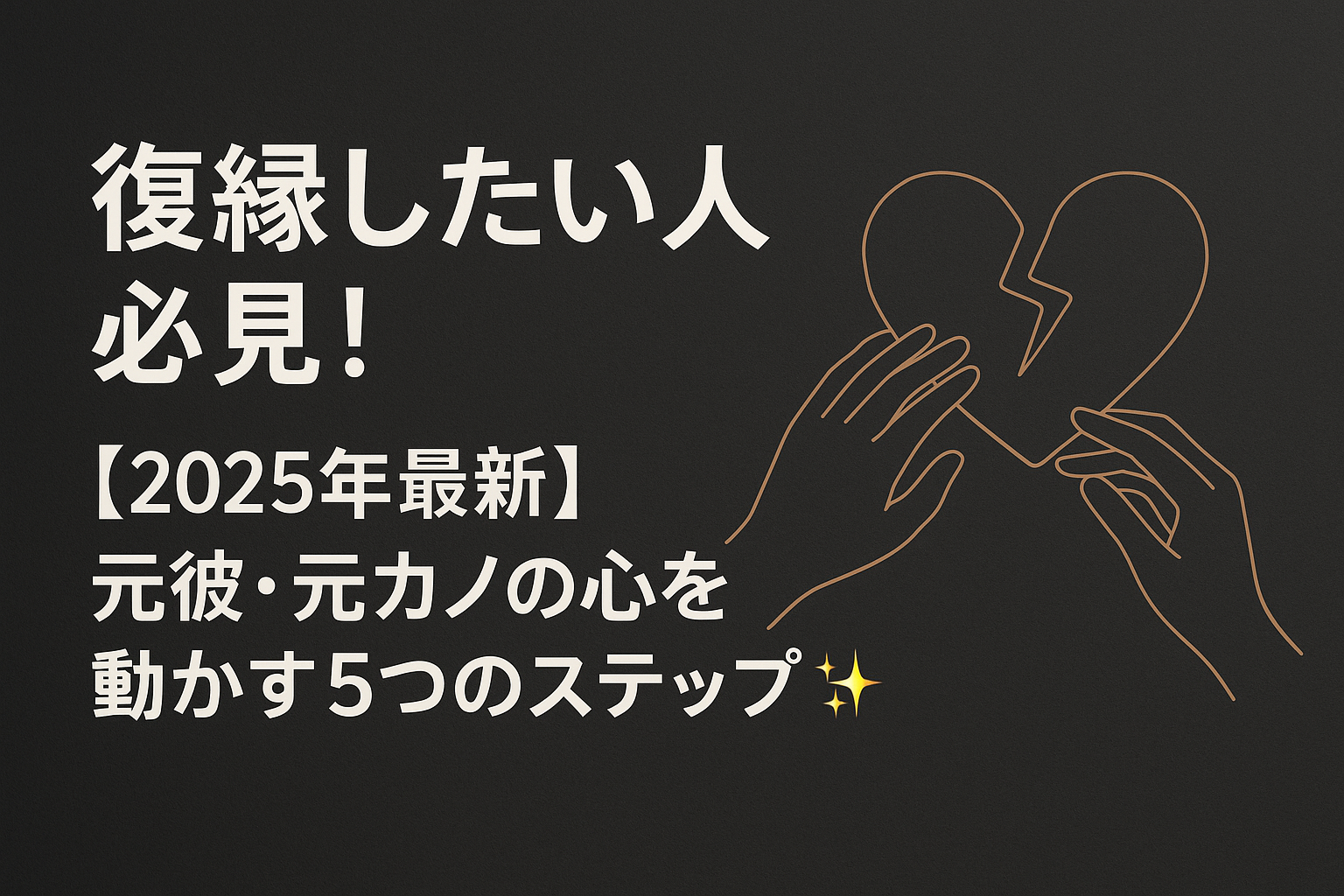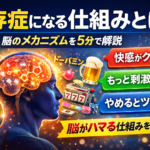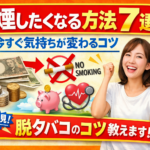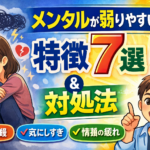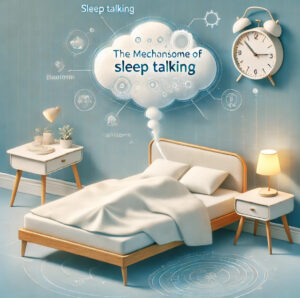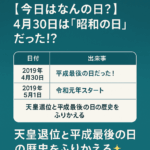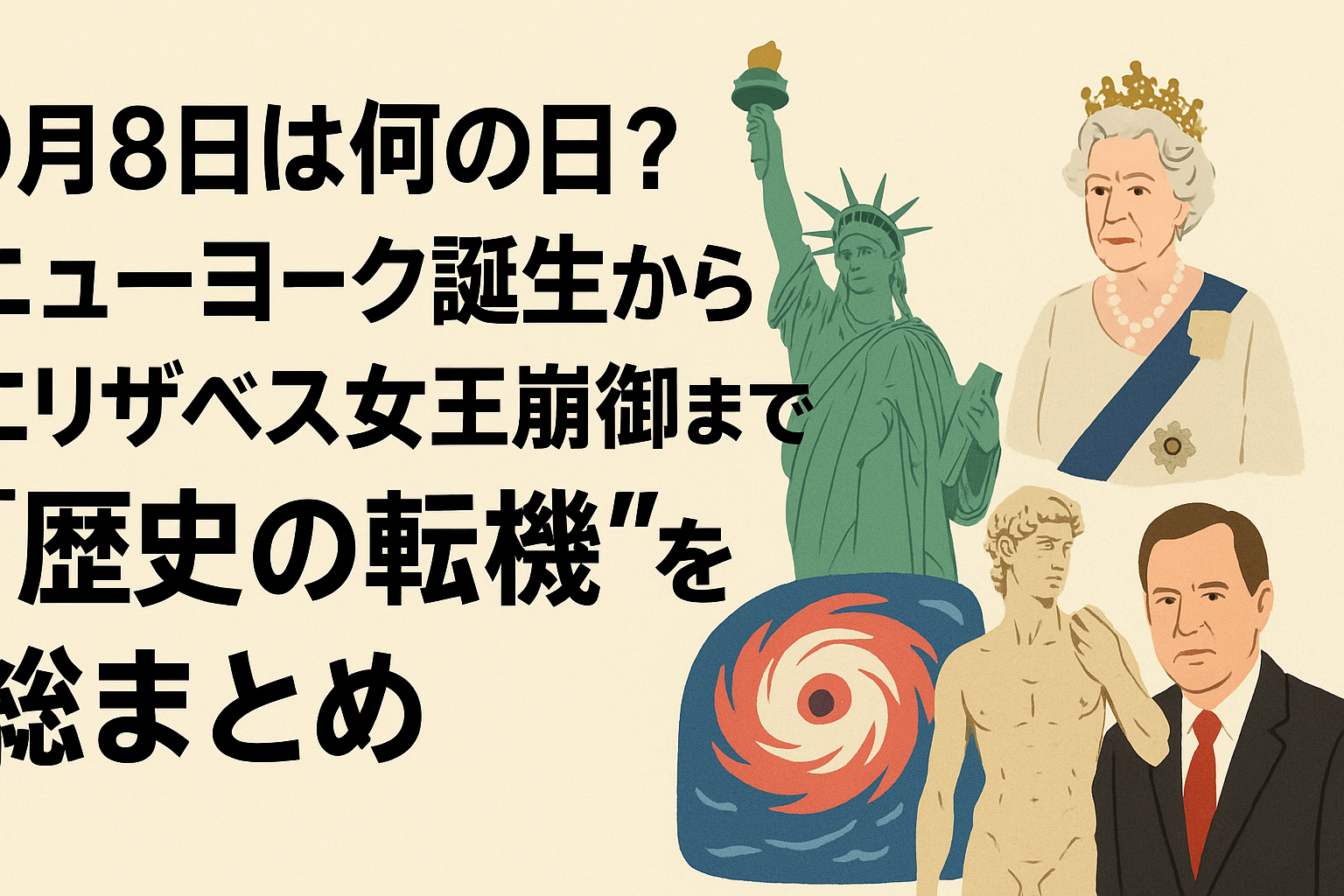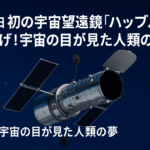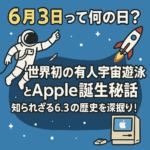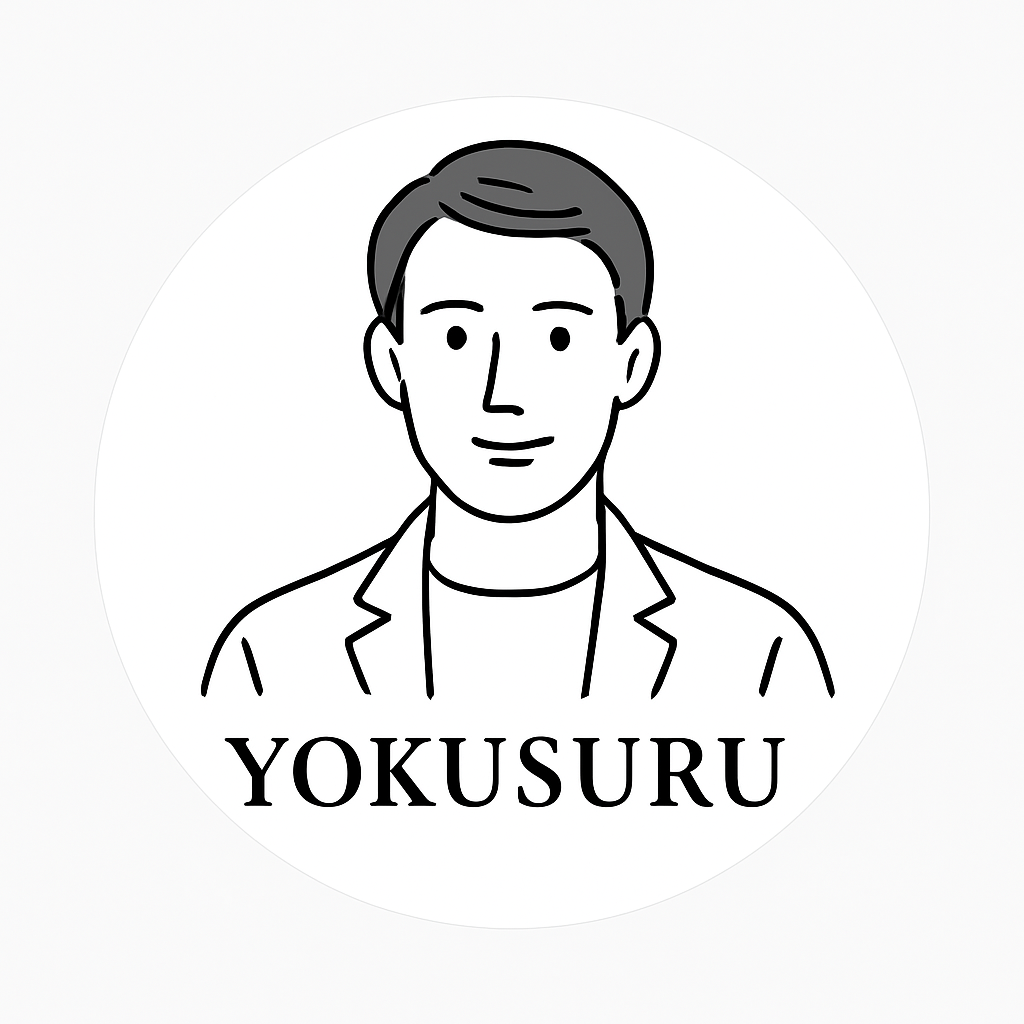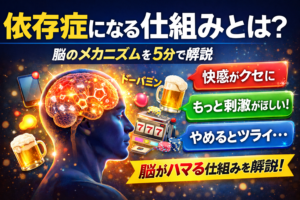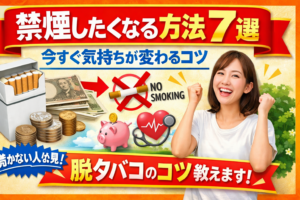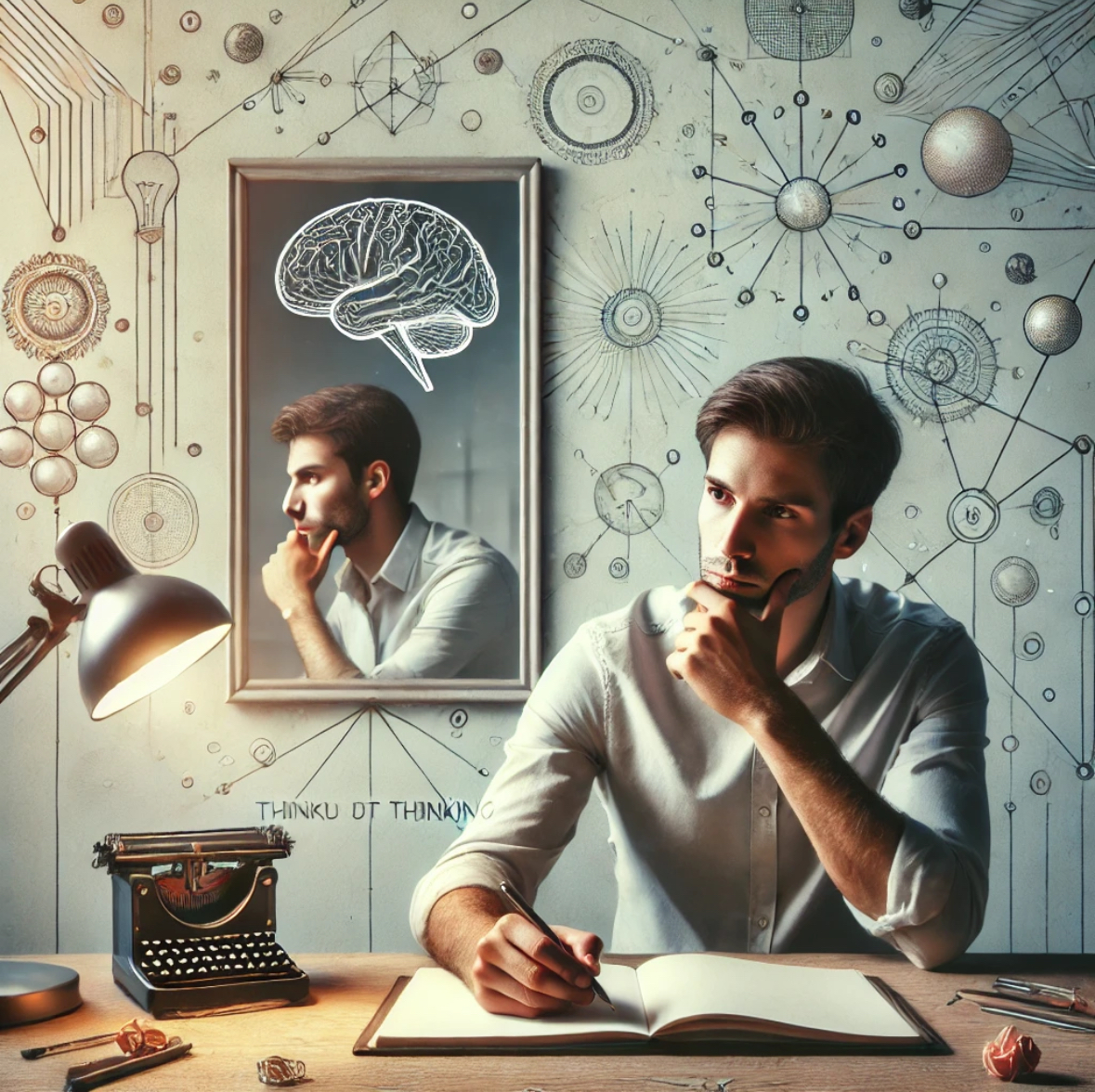
現代の複雑な社会やビジネス環境において、「メタ思考」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
今回は、この「メタ思考」という考え方について、初心者の方でもわかりやすく解説していきます。
- 「メタ」とは何か?
- メタ思考がどのような場面で役立つのか?
- 実生活や仕事にどう活用できるのか?
これらを詳しく掘り下げていきます!
メタとは?基本的な意味を理解しよう
「メタ」という言葉は、ギリシャ語の「meta」に由来し、「超えて」「高次の」「俯瞰する」という意味を持っています。
日常生活では、「メタ〇〇」という形で使われることがあり、たとえば以下のような例があります。
- メタデータ:データを説明するデータ(例:写真の撮影日や位置情報)
- メタ認知:自分の考え方や行動を客観的に捉えること
つまり、「メタ」という言葉がつくと、それ自体を一段上から見たり分析したりすることを意味します。
メタ思考とは?具体的な定義
「メタ思考」とは、物事を単純に捉えるのではなく、一段上の視点から考える思考法です。
たとえば、ある問題について「なぜこの問題が起きているのか?」と考えるだけでなく、「そもそも自分はなぜこう考えているのか?」や「この問題の背景にある構造は何か?」といった視点で掘り下げていきます。
具体例で考えてみよう
- 通常の思考:「このプロジェクトが進まないのはAさんのスケジュールが詰まっているからだ」
- メタ思考:「そもそもなぜAさんにばかり負担が集中しているのか?」「このプロジェクトの体制に問題があるのではないか?」
このように、物事を表面的な原因だけでなく、構造や仕組みの視点からも捉えるのがメタ思考です。
メタ思考のメリット:何に役立つのか?
1. 問題解決力が向上する
メタ思考を活用すると、表面的な原因だけにとらわれず、本質的な問題を見抜く力が身につきます。
「なぜ?」「そもそも?」と問い続けることで、根本的な改善策を考えられるようになります。
2. 自己成長を促進する
メタ思考の一部である「メタ認知」を使うと、自分の考え方や行動を振り返り、改善することが可能です。たとえば、「なぜ自分はこの場面で怒ってしまったのか?」と考えることで、感情をコントロールするスキルが向上します。
3. コミュニケーションがスムーズになる
相手の意見や立場を俯瞰的に見ることで、対立を避け、建設的な議論ができるようになります。たとえば、チーム内のトラブル時に「なぜ相手がそう考えるのか?」を理解することで、解決策を見つけやすくなります。
メタ思考を鍛えるための3つのステップ
- 「なぜ?」を繰り返す
ある事象や問題について、「なぜそうなるのか?」を5回以上掘り下げて考えるようにしましょう。
たとえば、「売上が落ちた」という問題に対して、「なぜ売上が落ちたのか?」「なぜ顧客が離れたのか?」と深掘りします。 - 視点を変えてみる
自分以外の立場や状況を想像し、「他の人ならどう考えるか?」「全体から見たらどう見えるか?」といった多角的な視点を意識してみましょう。 - 振り返りを習慣化する
1日の終わりに、自分の行動や考え方を振り返る時間を作りましょう。「今日の判断は正しかったか?」「もっと良い方法はなかったか?」と自問自答することで、自然とメタ思考が鍛えられます。
実生活での活用例
例1:職場の問題解決
メタ思考を使うと、チームのトラブルが起きた際に、「誰が悪いのか?」ではなく「どうすればこの問題を防げる仕組みを作れるのか?」と建設的に考えられるようになります。
例2:自己管理
「なぜ自分は最近疲れを感じているのか?」を考えることで、生活習慣や仕事量を見直し、改善策を実行できます。
例3:人間関係
友人や家族と衝突した場合でも、「相手はなぜこう感じたのか?」「自分の言動に問題がなかったか?」と振り返ることで、より良い関係を築けます。
まとめ:メタ思考は誰にでも役立つ万能ツール
「メタ思考」とは、一歩引いた視点で物事を捉え、より本質的な理解や解決策を導き出す思考法です。
このスキルを身につけることで、問題解決力や自己成長、人間関係の質が向上します。最初は難しく感じるかもしれませんが、「なぜ?」と問い続ける習慣をつけることで、誰でも自然と身につけられるものです。
ぜひ、今日からメタ思考を実生活に取り入れてみましょう!