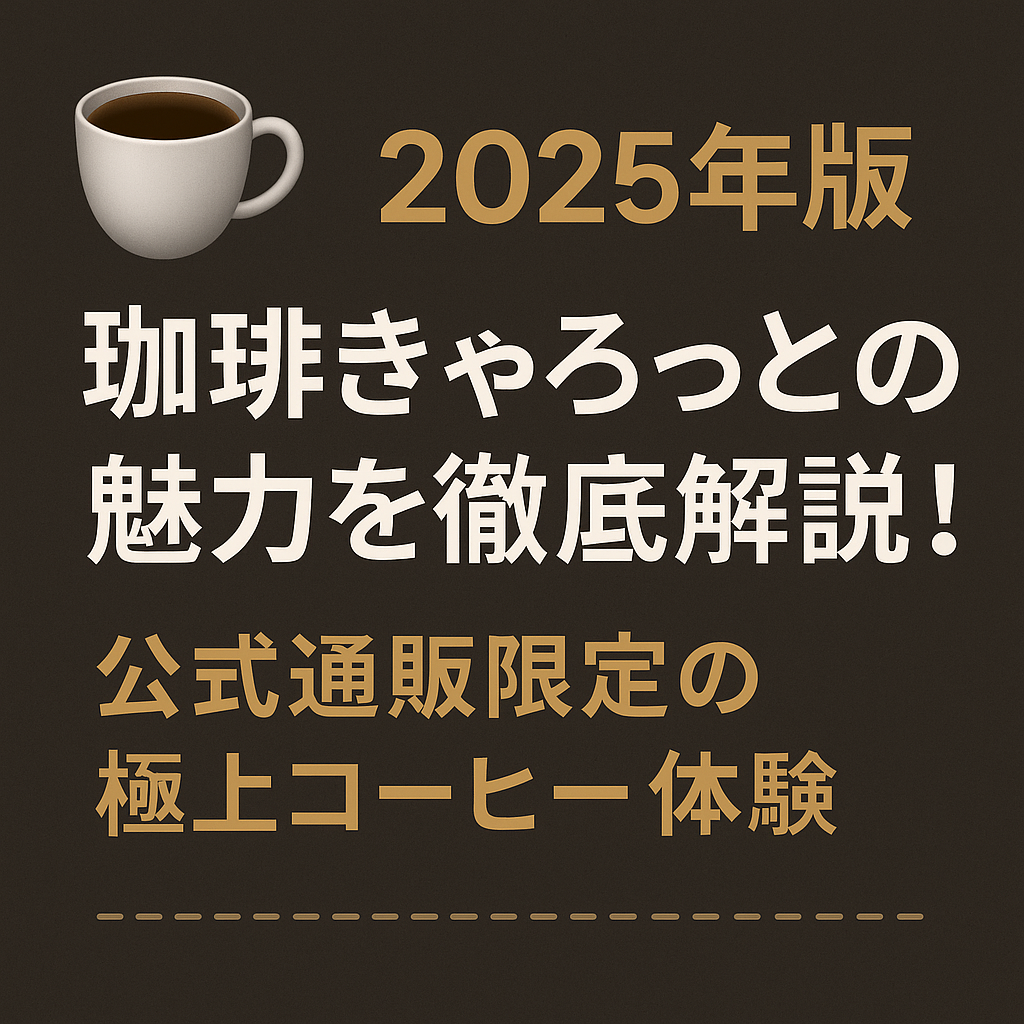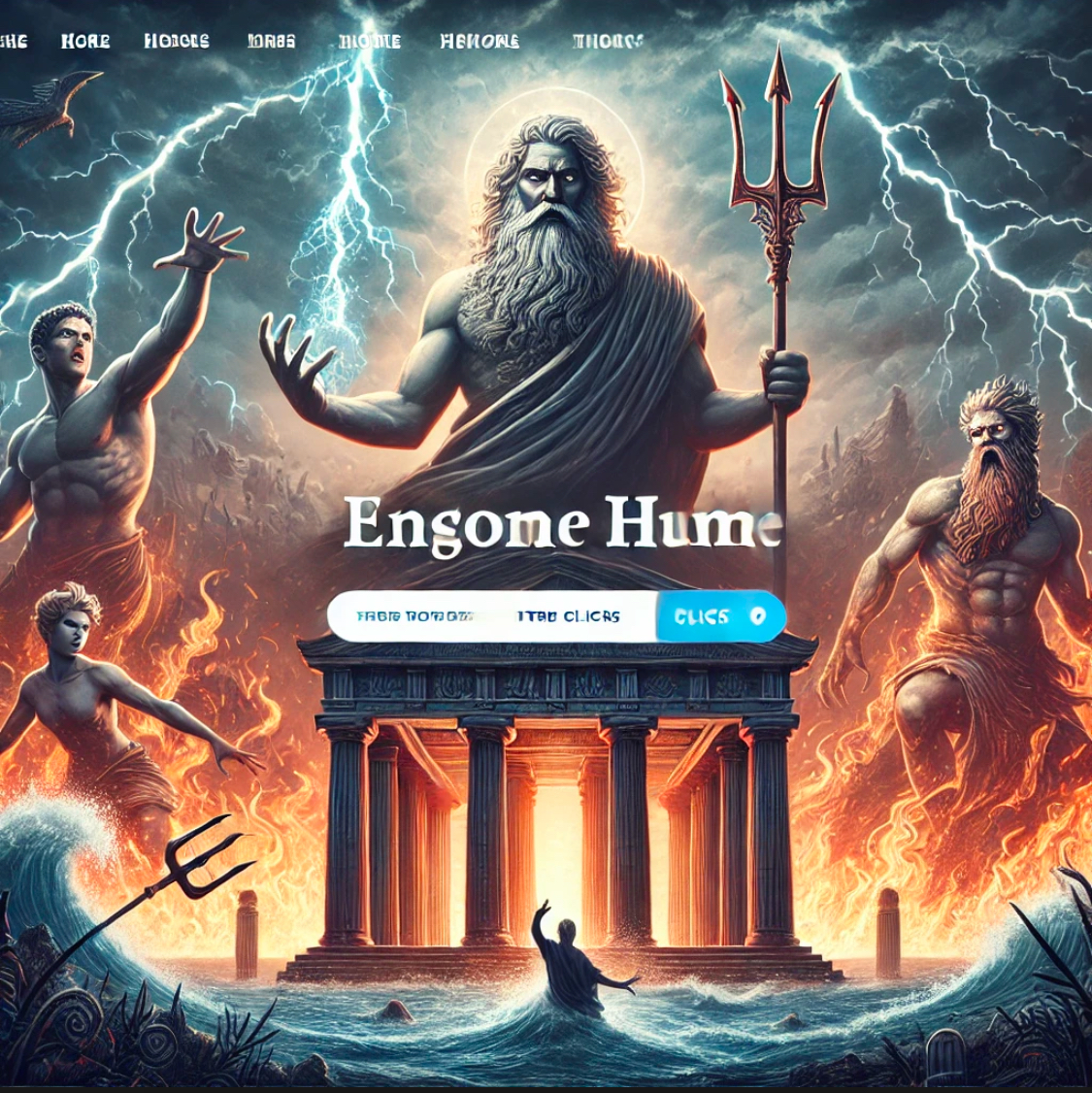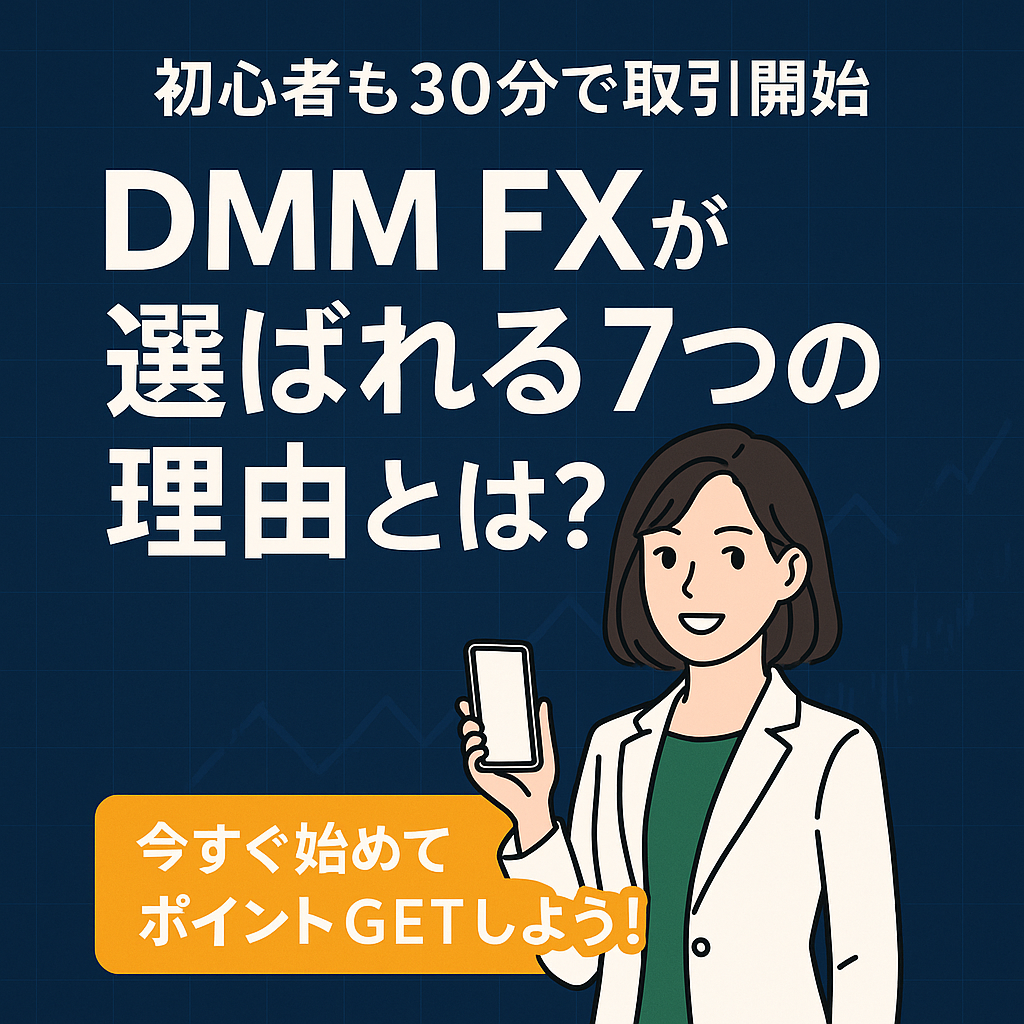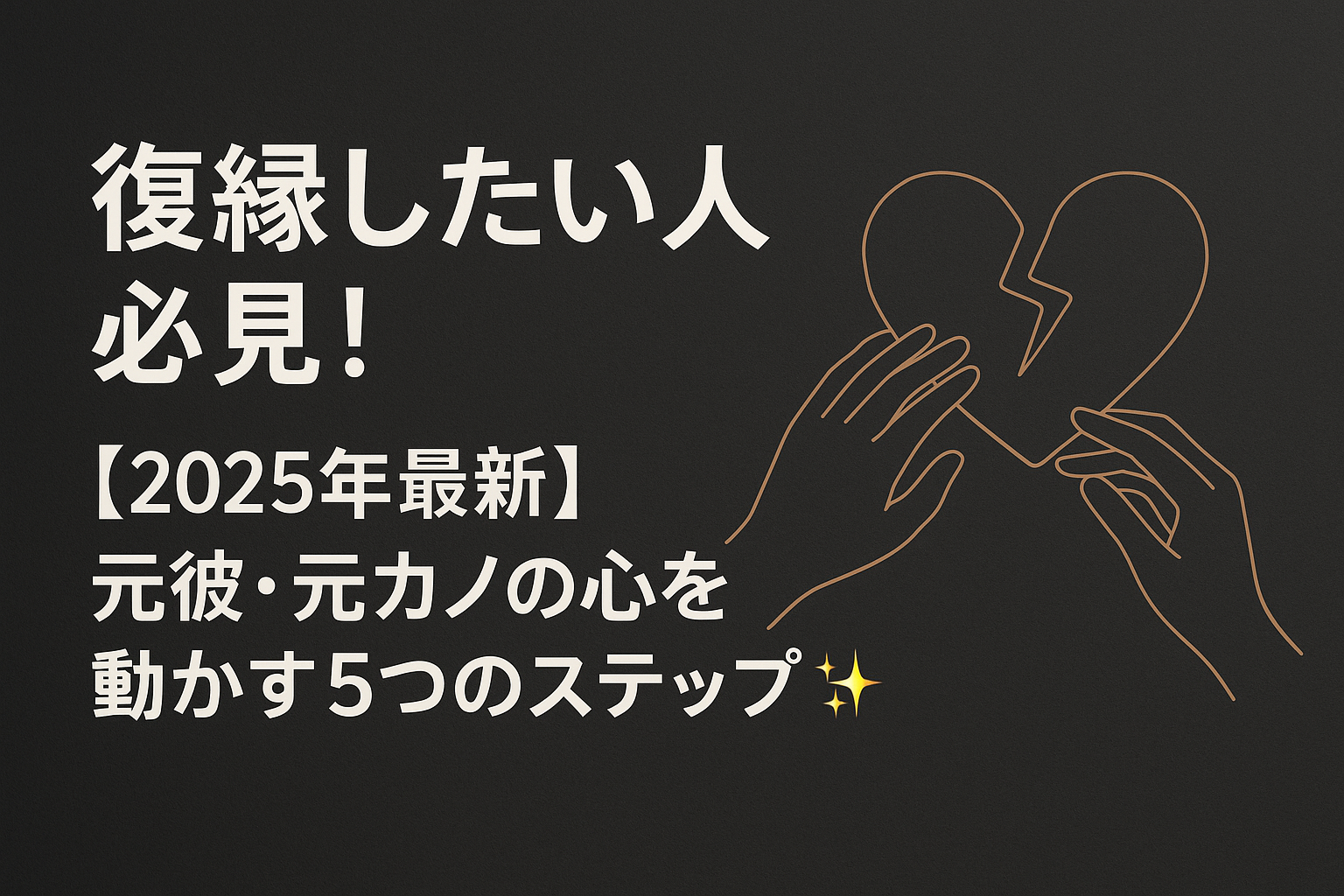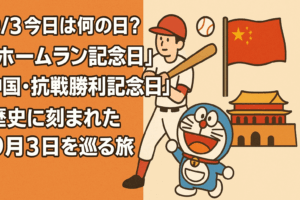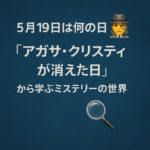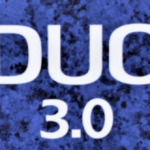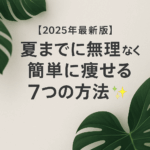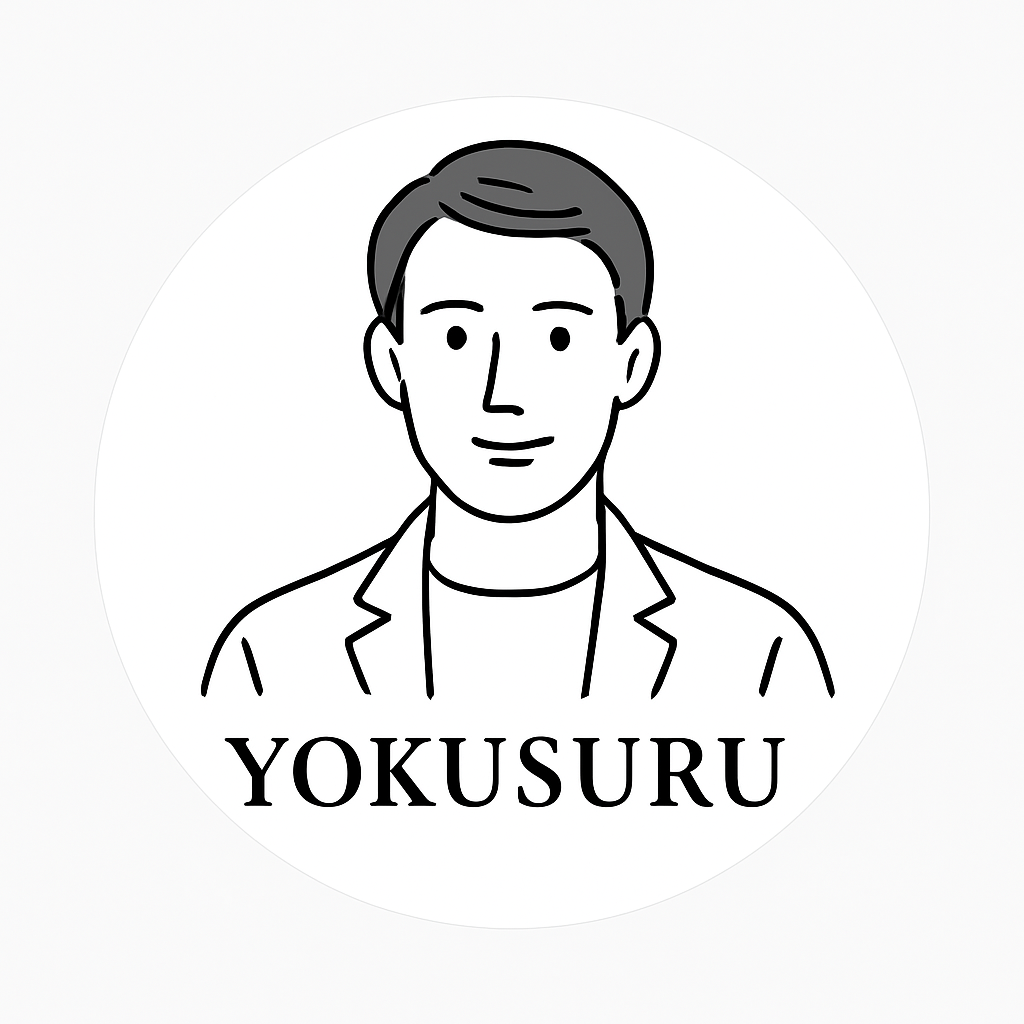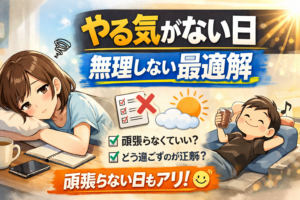こんにちは、るるです🌸
今日は 9月2日 にちなんで、歴史的に大きな出来事の裏側を振り返ります。
1923年9月1日、関東地方を襲った 関東大震災 は、日本の近代史において最も大きな災害の一つでした。
では、その翌日 9月2日 に人々はどのように動いたのでしょうか?
震災の翌日に起きた出来事を知ることで、「災害後の社会の動き方」や「私たちが学ぶべき教訓」が見えてきます。
🏚️ 9月2日の状況 ― 混乱から立ち上がる人々
関東大震災は9月1日正午過ぎに発生。首都圏の広い範囲が火災で焼失しました。
翌日の9月2日、人々は焼け跡の中で 避難生活の始まり を迎えます。
主な出来事を表にまとめてみました👇
| 日付 | 出来事 | 状況 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 関東大震災発生 | M7.9の地震、火災旋風で東京・横浜壊滅 |
| 9月2日 | 避難生活が本格化 | 上野公園・皇居前広場などに数万人が避難 |
| 9月2日 | 政府の動き | 内務省が臨時救護所設置、軍が炊き出しを開始 |
| 9月2日 | 社会の混乱 | デマが流れ、治安悪化の兆し |
この表からもわかるように、震災の翌日にはすでに「避難」「救援」「治安維持」という3つの動きが同時に始まっていました。
🍙 炊き出しと助け合いのスタート
9月2日、東京各地では 軍や地域の人々による炊き出し が始まりました。
火災で家を失った人々にとって、温かい食事は大きな希望となったそうです。
被災者の証言にはこんな声があります。
「9月2日の朝、初めておにぎりを配られた時、涙が出た」
この出来事は、まさに「助け合いの力」が人々を支えた瞬間でした。
⚠️ 社会不安とデマの拡散
一方で、9月2日には 根拠のないデマ が急速に広がりました。
「井戸に毒を入れられた」「暴動が起きる」といった噂です。
混乱の中で冷静さを失うことは、災害時に最も危険なこと。
この経験から学べるのは、現代でも 情報リテラシーの大切さ です。
📌 現代への教訓 ― 9月2日をどう活かす?
関東大震災の翌日である9月2日は、混乱と助け合いが同時に始まった日でした。
私たちが学べるポイントをまとめると👇
| 教訓 | 内容 |
|---|---|
| 助け合いの大切さ | 災害時は地域・人とのつながりが命を守る |
| 食の安心 | 炊き出し・物資支援が人々の希望になる |
| 情報の正確さ | デマに惑わされず、信頼できる情報源を確認する |
| 早めの備え | 日常から防災用品・食料備蓄をしておくことが重要 |
🌱 まとめ
9月2日は、 「絶望の中で希望を探し始めた日」 といえるのではないでしょうか。
100年前の出来事ですが、災害の翌日に人々がどう動いたかを知ることは、現代に生きる私たちにとっても大切なヒントになります。
👉 防災グッズを見直す
👉 情報の出どころを確かめる
👉 日常的に「助け合い」を意識する
これらを意識して、私たちも未来の災害に備えていきたいですね。
それでは、また明日の更新で🌸